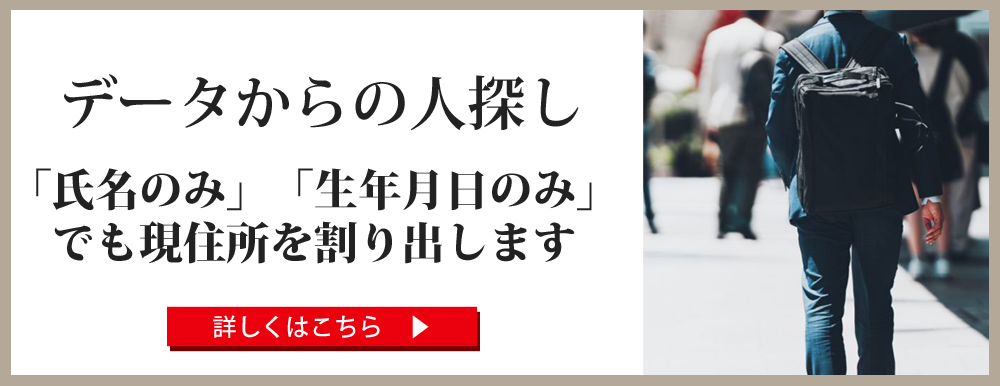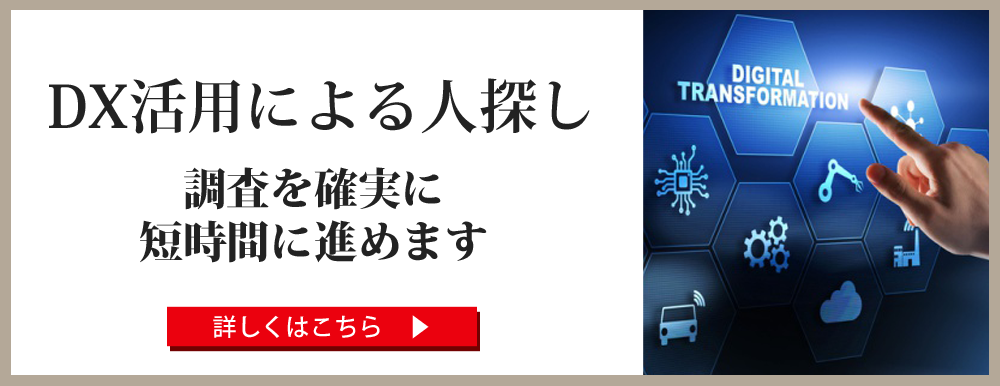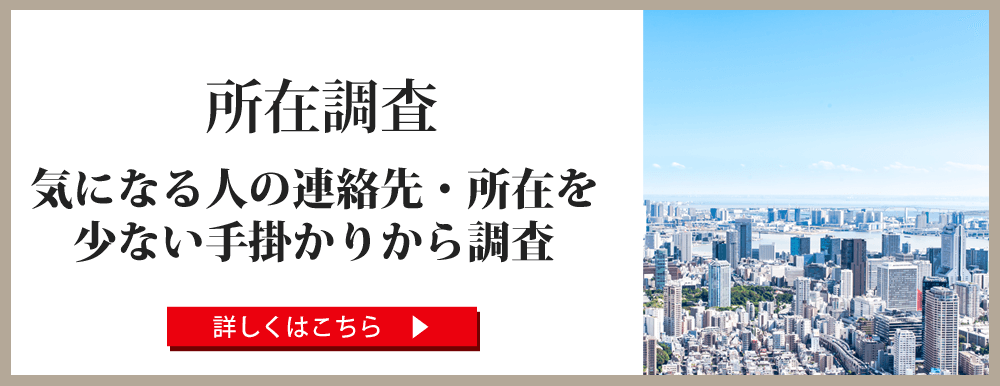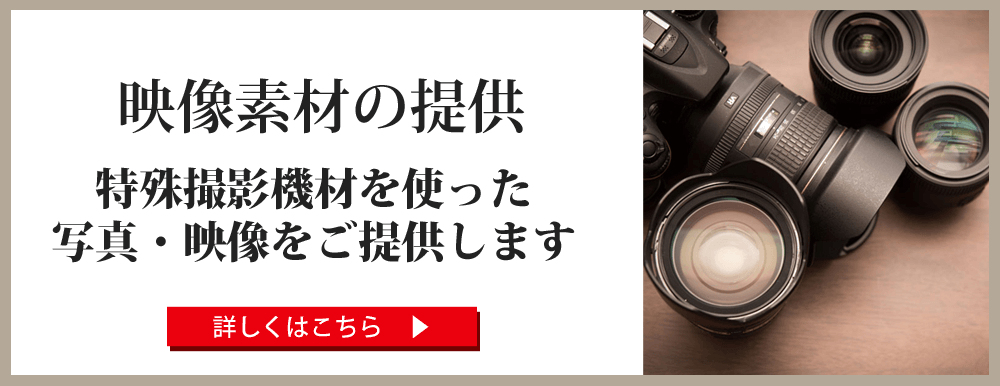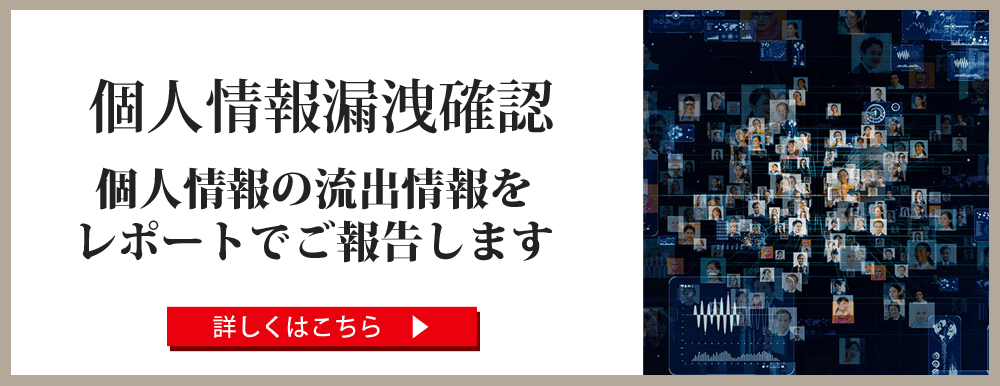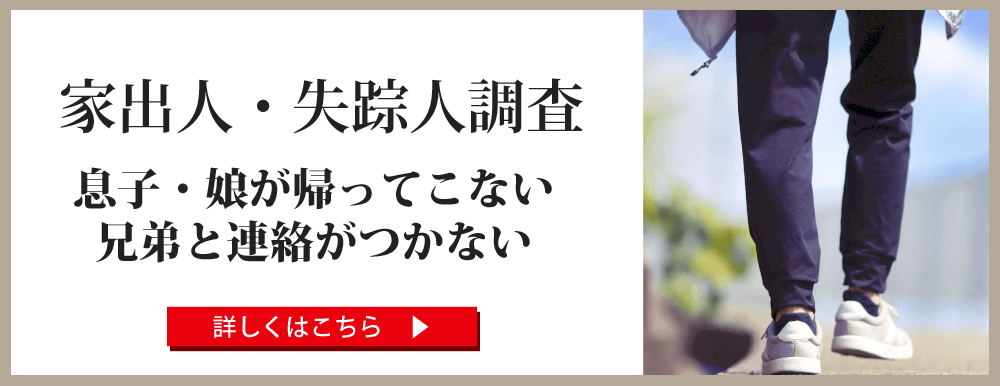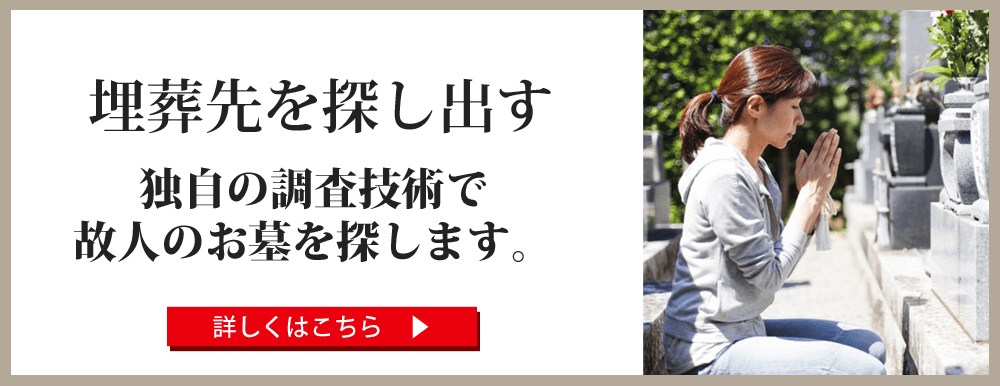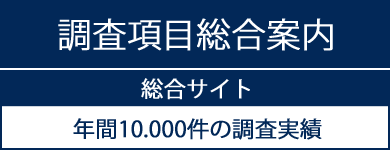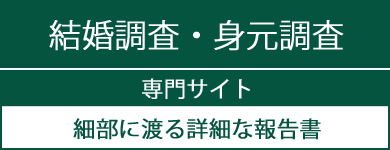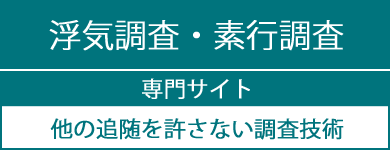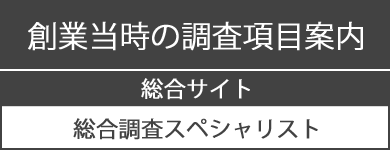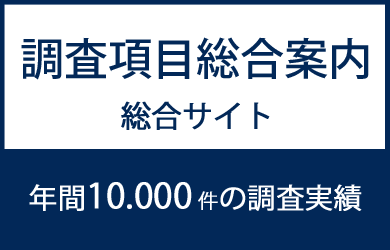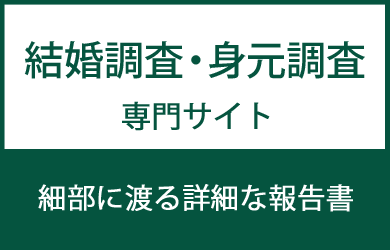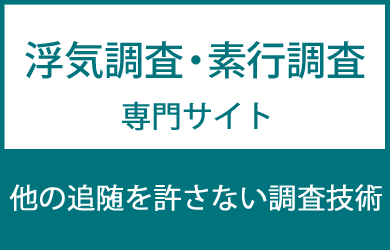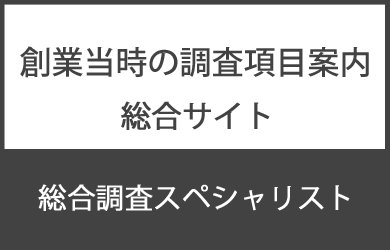探偵の執念が実を結ぶ
家出人捜索は
決して簡単ではありません
埋葬先を探し出す
埋葬先を
探し出す
実母の埋葬先を探した事例
調査業に長年携わっていると、時として神懸かりに思え、背筋が寒々しく思える事がある。
今から記す内容は、まさにそのことを裏付ける出来事であり、まるで死者の魂が調査員の身体を借りて、依頼者の目的に向かわせたとでも思える案件であった。
それは、日射しが身にしみる真夏の暑い日のことである。
50歳代初老の婦人が当社を突然訪れ、「墓を探して欲しい。」と言う。都内在住で、物腰が柔らかく、高価そうな服を身に付けた生活にもゆとりを感じさせる婦人である。依頼内容に対し即座には理解できぬまま辛抱強く耳を傾けていると次のような内容であった。

この婦人の話を要約すると”ある日突然実母が亡くなったという知らせを聞いた。それ迄、姉妹間の問題で母親と別居していたが、母親との確執では無く、実姉との意志の疎通が出来ず縁遠くなっていた。結果死亡後、相続問題が起因し、実姉とのいざこざが増大、実母の葬儀日や埋葬場所すら教えて貰えなかった。全て事後判ったことだった。いくら姉との確執があったとしても、実母の墓の場所を知らないのではいたたまれず、これまで何度も弁護士を通じて姉に哀願したきたが、全く聞き入れてもらえなかった”と云うことである。
そこで、この婦人は、身内の恥を晒すことも覚悟の上で、当社のドアを叩いたという経緯であった。
人を捜す事に掛けては手慣れていても、事「墓」の場所となると全く経験がなく、どんなものか見当もつかぬまま、とりあえず姉の住居周辺や公簿書類、果てには、姉やその関係者に根気強く聴取を続けて行った。姉側のガードは思いの外固く、長年を経て生じた姉妹間の確執を改めて思い知らされた。
依頼を受けてから、丸2ヶ月が経過した。
ようやく「火葬証明書」を入手して

当然すぎる事ながら墓の場所は、それを知る人物から入手しないと判明しない。その人物が、頑としてガードを固めているとなると、もうお手上げ状態である。せめておおよそのエリアだけでも判れば片っ端から当たることもできるが、それもできずじまいである。
調査経緯で判ったことだが、埋葬場所(墓の場所)は、墓の場所を移す改葬の場合と異なり、特別に管轄の役所へ届け出る義務もなく、その為、埋葬場所に関しては記録も残っていない。
(調査当時・以下同じ)
やむなく、これまでの経緯と今後の進展の期待ももてない旨伝えると、落胆の色は隠さず、予期していたのか依頼者自身も納得はするが、どうしても諦めがつかない様子であり、再度懇願されてしまった。
新たな展望も見いだせぬまま、これまでの経緯を振り返り、着眼点はないか再検討してみるが、同様である。
あれこれ思案しても良案は浮かばず、やむなく重い腰を上げ、再度原点に戻り、依頼者から受け取っていた委任状を手に母親が生前居住していた当該の役所へ向かった。
ご存じの事と思うが、人が死亡すると荼毘に伏せるための「火葬許可証」と納骨のための「埋葬許可証」を発行して貰う。
前者は、役所に記録が残るが、後者は特別記録はない。当方が欲しいのは後者の方であるが、他に方法も見出せず、回り道とは思えても記録が残る前者から当たるしかない。
あらかじめ断っておくが、当初も当該の役所で「火葬許可証」を入手すべく努めたが、特殊な証明書故、前例がなく断られてしまったという経緯がある。尚、両者は便宜上、「死体火葬許可証」一枚で処理する場合が一般的となっている。火葬場所は決定しているが、埋葬場所に関しては、故人の宗派や親族の意志等により、決まっていない場合がある為という。
再度委任状を提示し粘り強く事情説明を行ったところ、やっとの思いで証明書を受け取ることができた。ここで、前回よりは一歩前進したことになる。この証明書には、死亡者氏名・生前住所・死亡年月などが記載されている。この程度は当然依頼者が知るところであり真新しいものではない。
ただ、その下の欄に記された「何処の斎場で荼毘に伏されたか」という項目を見付けた時は身体の震えを抑えることが出来なかった。この唯一の頼みの綱とも思える斎場の名前と場所を入手した当方は、焦る気持ちを抑え斎場へ向かった。
葬儀社の名前が浮かぶ
これまで、斎場などとんと縁がなく、想像した事もなかったが、訪れて見ると驚愕する。
日に朝から夕刻までぎっちり予定が詰まり、これだけの人が亡くなっているのかと感慨を受け、見上げる大きな煙突からはもくもくと煙が立ち上っている状況である。
何か言いしれぬ神妙な気持ちのまま受付を訪ね、訪問の主旨を伝えると、当初怪訝な顔つきであったが、後日の連絡を交わし同所を後にした。
待つこと数日、斎場からの連絡はあった。「何月何日、確かに当方で受け付けています。当日は極く内々だけの少人数の方がいらしていたのを覚えており、密葬的な様相でした。その後は当然、埋葬されたことと思いますが、詳しいことは判りません。」と言った内容であった。

予期した事ながら、たんたんとした事の経緯を聞くと、日に何組もの火葬を受け持ち、個々の流れにさしたる感銘も受けず、言葉は悪いが半ば事務的に処理し特別な印象も残っていないのは仕方のないことかもしれないと感じると同時に、墓探しの細い手掛かりも途絶えてしまった。
事の次第を依頼者に報告しなければならないが、どうも気が重い。八方塞がりであり、他に手だてが思いつかず思考も固まらない状態である。諦めムードが漂よっているが、報告書を作成するにしても前回とさしたる変化もなく依頼者の悲痛な顔が浮かんでくる。
せめて最後に、当日の会葬者の中に見知った人は居なかったかどうかその日の斎場の担当者に直に会い、その結果、調査を打ち切ることを決心し、後日再び斎場へ向かった。
既に火葬日時が判っていた為、前回の訪問時よりかスムーズに事が運び、幸いにも当時の担当者が居てくれた。担当者の話も電話内容とほぼ同じであり、参列者にも見知った人は居なかったらしく、耳目を引く話は聞かれなかったが、この担当者は葬儀一式を受け持った葬儀社の名前を記憶していた。
この葬儀社は、冠婚葬祭事業全般を行い、全国的にも名前が知られている大手である。 葬儀だけでも日に何組も受け持っている。
事前に連絡し、当時の担当者名を聞くことも考えたが、当方に残された唯一の情報源であり、下手に小細工をせず、直に会って真っ正面から直接尋ねることにした。
探し求めた埋葬場所へ

都内の一等地に建つビルの入口には、中小の同業他社を威圧するかの如く、大きな社名を冠し、ロビーには受付まで設けてある。
火葬場同様葬儀社にもとんと縁のない当方が、この会社の社員の一人から、数ヶ月前のそれも書類上には残らない埋葬場所をたどらなければならない。全て当人の記憶に頼らなければならない事であり、全く持って憂鬱な気持ちになってくる。
まず受付を通じ葬儀内容の問い合わせをする。すると担当者を呼んでくれ、応接室に案内された。話を切り出すタイミングが問題であり、「客ではない」と判断されると態度が一変する事だって考えられる。
いかにも葬儀一切の依頼をするかの如く興味を引きつつ、「ふと思い出したかのように」切り出した。「そういえば最近、私の知り合いもここで葬儀を行っているはずですが。」すると当然「どなたでしょう」と返ってくる。後はこちらのペースで話を進め、当時の担当者のリストを持って来て調べてくれた。結果、式を取り仕切った担当者は当日不在で、担当者名を記憶に留め、同社を後にした。
当方に残された最期の情報、長い日数を経てようやくたどり着いた、たった一人の氏名。
しかしながら、この人物が果たして埋葬場所を承知しているものなのか?既に数ヶ月を経過している。日に何組もの葬儀を担当し、全く記憶にないかもしれない。一刻も早く話を聞きたいはやる気持ちと駄目かもしれない深憂が交錯する。
あれこれと考え倦ねたが結論が出ない。下手な小細工も当人が知らなければ意味を為さない。
結局、再び同社を訪れ正面からぶつかることにした。
すると、当方の意に反し、当人の口からいとも簡単に埋葬場所のヒントが伝えられた。
散々苦労しても判る時はこんなものである。
事の経緯は全くの偶然らしい。
通常、火葬が終われば遺骨を渡し担当業務は終わり、次の予定に移行するらしいが、その時はたまたま参列者の中に顔見知りがおり、その者との話の中に埋葬場所が出たと言うことである。
かなりの日数が経過しており、あいまいながら記憶の断片を辿って貰うと「港区内のお寺・それも
「 麻布近郊」と言う情報が得られた。後はこの担当者の記憶の確かさを信じ、該当地域を端から当たる事となるが、周知の如く港区内には多数のお寺が点在している。
そのお寺の一つに当方の目指すものはあった。
「確かにうちにお墓がありますよ」
そう話す住職の声が、まさに神様の声に思えたものである。
Service
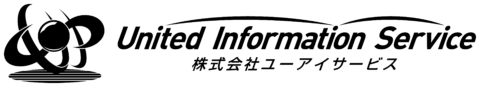
埼玉本社
埼玉県公安委員会 探偵業届出証明番号 第43210047号
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 RPH浦和B1F
TEL:0120-15-0011 (調査相談直通)
TEL:048-827-0111(代表)
TEL: 048-826-7700(総合案内)
FAX:048-810-1400
大阪・面談室
大阪府公安委員会 旧探偵業届出証明番号 第62120303号
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-1-3 大阪駅前第3ビル23階7-3
TEL:0120-45-1611 (調査相談直通)
TEL:06-6225-7209 (総合案内)
FAX:06-6225-7394
仙台・委託
宮城県公安委員会 探偵業届出証明番号 第22070129号
〒980-0803
宮城県仙台市青葉区国分町3-1-4 ムサシヤビル4階
TEL:0120-15-0011 (調査相談直通)
東京統括本部・面談室
東京都公安委員会 探偵業届出証明番号 第30090128号
〒163-1030
東京都新宿区西新宿3-7-1 新宿パークタワーN30階
TEL:0120-15-0011 (調査相談直通)
TEL:03-5326-3604 (総合案内)
FAX:03-5326-3001
長野・委託
長野県公安委員会 探偵業届出証明番号 第48071240号
〒380-0803
長野県長野市三輪6-26-2-2階
TEL:0120-15-0011 (調査相談直通)
中部統括本部・面談室
〒450-0002
愛知県公安委員会 探偵業届出証明番号 第54120020号
愛知県名古屋市中村区名駅4-6-23 第3堀内ビル9階
TEL:0120-59-9955 (調査相談直通)
TEL:052-589-7176 (総合案内)
FAX:052-589-7001
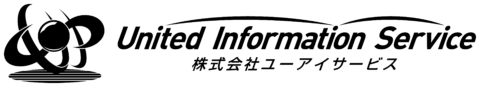
総合調査ユーアイサービス
〒330-0062
埼玉県さいたま市浦和区仲町2-5-1 RPH浦和B1F
TEL:0120-15-0011